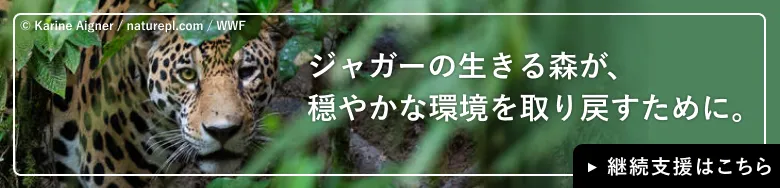ジャガーの棲む森:保全活動の現場アマゾンを訪ねて
2025/09/26
活動視察のため、アマゾンで実施しているジャガー保全プロジェクトの現場に行ってきました。
足元から地平線まで続く、大小さまざまな木々の景色。
ここは、ブラジル北部のアマパ州に広がるアマゾンの森、私たちがジャガーの保全に取り組む、プロジェクトの現場です。

ジャガーは中南米の生態系の頂点に立つ動物ですが、生態や個体数などは、まだまだわからないことばかり。
そこで、私たちのプロジェクトではまず、このアマパ州で生息調査から開始しましたが、その中で、生息域の各地で近年、「人とのあつれき」の懸念が、高まっていることがわかってきました。

本プロジェクトで設置した生息調査用のカメラトラップが捉えたジャガー。「あつれき」の問題は、こうした森の周辺にある放牧地や人の居住地に現れたジャガーが、家畜を襲うなどの被害をもたらすことで生じています。
2024年からは、アマパ州立大学と協力して、この問題の実態調査を併せて進めていくことにしました。
私たちも、その現場を訪問。
保護区内で代々居住されている先住民の方のご家族にお話を伺ったところ、家畜被害を避けるため、また、子どもの安全や通学面の利便性を考えて、住居を森の中から幹線道路沿いまで移動させたことなどを、話してくださいました。
野生動物による被害はジャガーに限ったものではありませんでしたが、そうした実態を知ることは、保全活動を進める上で重要な情報です。


「人とのあつれき」の実態調査では、社会学調査の手法を活用して、保護区のステータスの違う2カ所でヒアリングを実施し比較。今回訪問したのは「リオ・カジャリ採集保護区」:先住民のみが居住を認められている保護区で、商業的な活動に制限があります。保護区内に20くらいの集落が点在していて、今回、7家族が暮らす集落「Vila Nova」を訪問しました。

Vila Novaにある休憩所にて。店主が採集したブラジルナッツをふるまってくれました。この地域では近年、家畜で生計を立てるより、ブラジルナッツ採集やアサイー栽培に生業を切り替える家庭が増えています。これは、野生動物による家畜被害を回避する手段になりますが、採集時にジャガーなどと遭遇する危険があります。
こうした取り組みを実施するには、まず地域の信頼を得なくてはなりません。
その土地ならではの事情や、言葉遣いなども理解しておく必要もあります。
一緒に調査に取り組んでいるアマパ州立大学の教授も、こうした点の重要性を考慮した上で、社会学的手法を取り入れた調査・研究を進めています。

集落訪問後のミーティング。「人とのあつれき」の実態調査で協働している、アマパ州立大学の生物/社会学研究者のハーバート教授と。
地域で行なう野生動物の調査は、動物だけを相手にするものではありません。
道のりは長く、継続した取り組みがとても重要です。
日本の皆さまのご支援により、スタートすることができたこの取り組みを、これからも現地の仲間や地域の方々と一緒に進めていきたいと思います。