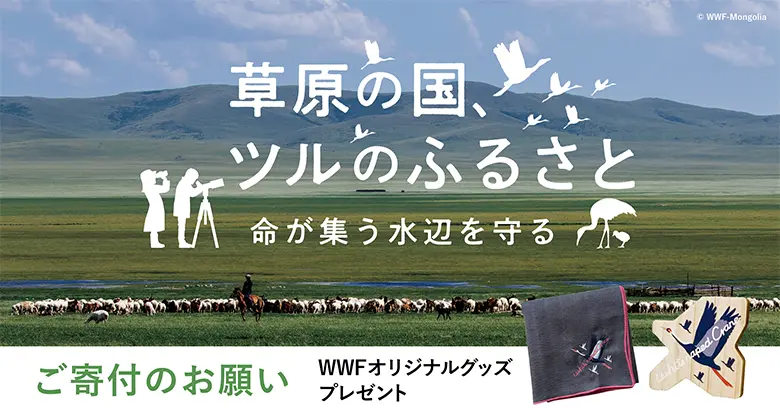愛鳥週間に寄せて
2025/05/13
毎年5月10日から16日までの一週間は、野鳥保護の大切さを知ってもらい、広めていくための愛鳥週間です。50年以上前に(公財)鳥類保護連絡協議会によって制定されました。
連休中にバードウォッチングを楽しんだ方もいらっしゃることでしょう。
私たちが皆さまのご支援のもと、ユキヒョウの保護活動に取り組んでいる西ヒマラヤにも、多くの鳥が生息しています。なかでも象徴的なのがオグロヅルです。

和名はオグロヅル( Grus nigricollis )ですが、英名はBlack-necked Crane (首の黒いツル)です。体高は140cmほどで、植物や昆虫、爬虫類を食べます。







西ヒマラヤに生息する野鳥。水鳥から猛禽まで多様な鳥が生息しているのは、草原、高山、湿地などさまざまな環境があるからです。
オグロツルは、夏場に標高の高いラダックへ飛来し、湿地で繁殖します。私も川辺や湿地に座り込んで抱卵している様子を目にしたことがあります。
現地では幸福の象徴とされていますが、開発による生息地の劣化や減少で絶滅のおそれが高まっています。
近年さらに脅威となっているのが外来種です。ラダックでは、野生化し人の手を離れて世代を重ねるようになったノイヌ(野犬)が巣の卵、抱卵中の親鳥や孵化した雛を襲うのです。

ユキヒョウ保護プロジェクトのフィールドであるチャンタンのプンゴック集落で確認された野犬に襲われたとみられるオグロヅル
ツォモリリ(モリリ湖)では、野犬の影響でオグロヅルを含む鳥の営巣地がまるごとなくなったそうです。
以前は市街地に限られていた野犬の活動範囲が拡大し、今や、こんなところに?と思うような場所でも野犬の姿を見ることがあります。
人や家畜が襲われる事件も起こっており、ラダックで野犬の問題は深刻化しています。
今後、草食動物やユキヒョウなどへの影響が出てくる可能性もあり、フィールドチームは、野犬の問題への取り組みも開始しています。
今の季節、まだ西ヒマラヤは厳しい寒さが残る時期ですが、夏をこの地で過ごす渡り鳥たちは、徐々にその姿を見せてくれることでしょう。

ラダック南東部のツォカー(カー湖)。冬は凍てつく寒さですが、春から秋は多くの鳥でにぎわいます。
現場で生じているさまざまな問題への対応を進めながら、生きものたちがより活動的になるシーズンの訪れを、楽しみに待ちたいと思います。