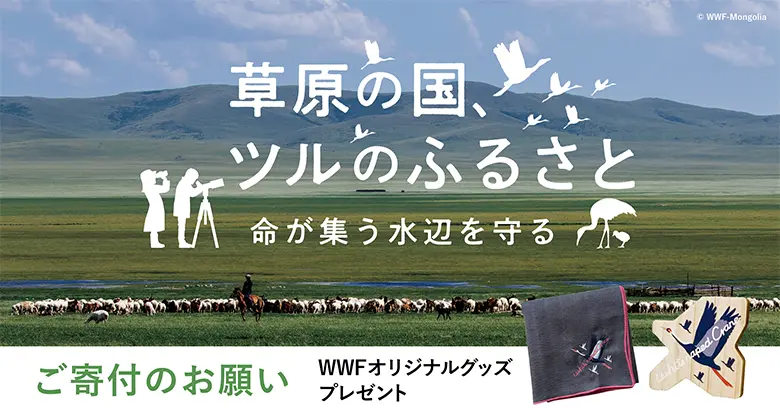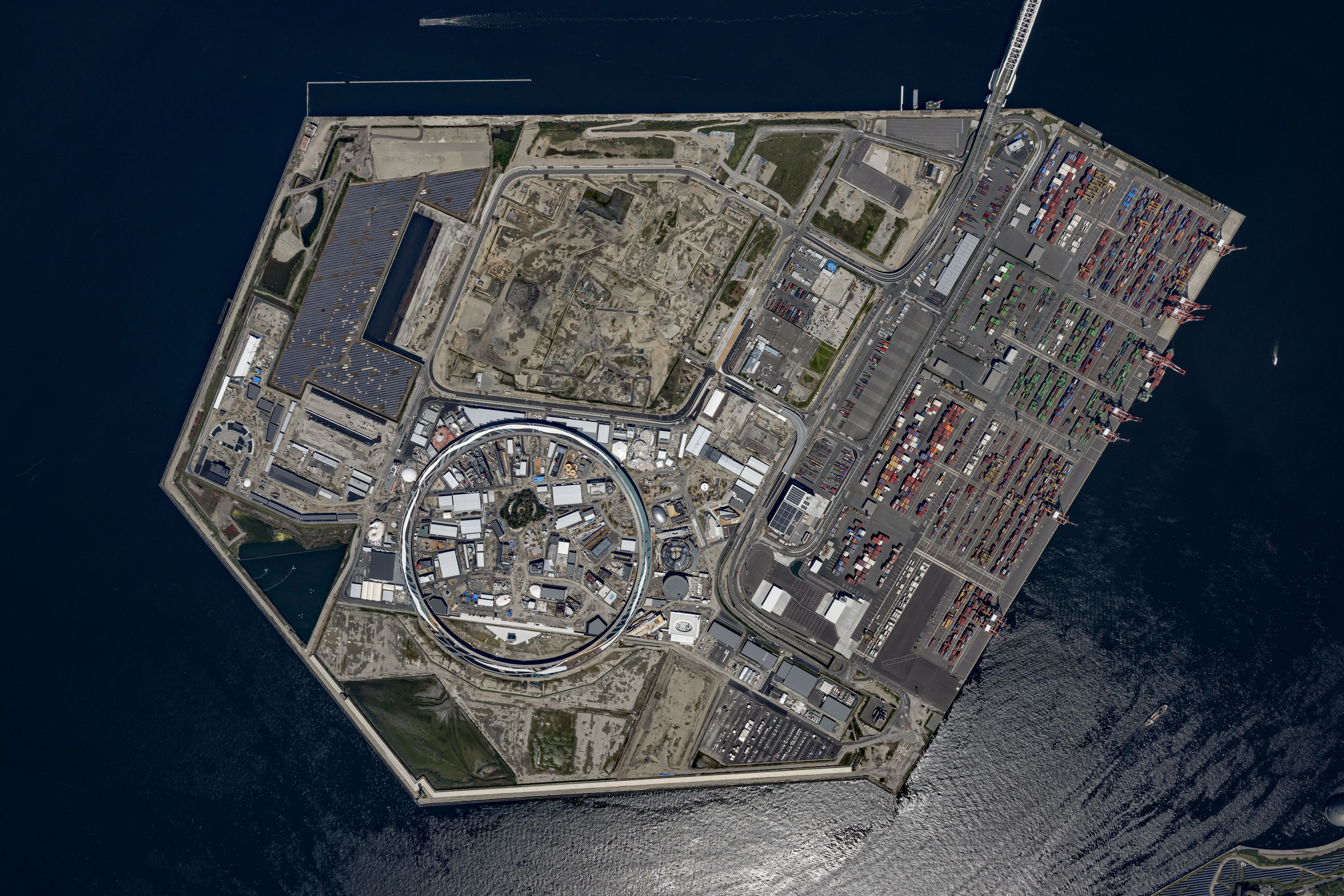「世界渡り鳥の日」子どもたちが守る人と自然の共生
2025/05/10
「共に生きる―鳥たちにもやさしい街と社会をつくろう(Shared Spaces: Creating Bird-friendly Cities and Communities)」
こちらは今年の「世界渡り鳥の日」のテーマで、人々と鳥たちの共生がメッセージです。
毎年5月と10月の第2土曜日は、国連が定める「世界渡り鳥の日」で、渡り鳥とその生息地を世界的規模で保全していく記念日です。
そんな今年の記念日である本日は、モンゴルで遊牧民の人々とマナヅルの共生を目指してがんばっている、子どもたちの取り組みを紹介したいと思います。

ここはモンゴル東部、アムール川の源流であるオノン川流域に位置するダダル村。
人口3,100人ほどの村で、チンギス・ハーン生誕の地として知られています。
村の外は広々とした草原地帯。草原のなかにある湿地には、IUCNのレッドリストで危急種(VU)とされているマナヅルが、子育てをしています。

マナヅルの親子。頭や身体が褐色の2羽は幼鳥。比較的浅い湿地や湿った草原を好んで暮らしています。
そんな自然豊かなダダル村で、私たちは、自然保護活動の頼もしいパートナー、小中学校のエコクラブの子どもたちにお会いしてきました。

エコクラブの子どもたち、学校の先生、WWFモンゴル、WWFジャパンのスタッフで記念に1枚。
エコクラブの子どもたちは、地域の動植物の学習、森林再生活動、マナヅルの観察やモニタリング、キャンペーンへの参加など、自然保護に向けた活動に取り組んでいます。
マナヅルの生息地保全では、自分たちの家族が遊牧を行なっている地域のツルの営巣場所や、各家が所有する家畜の数、飼われている犬の数などを調査。絵地図にまとめて発表してくれました。

マナヅルの繁殖地モンゴルでは、営巣地にウシやヒツジなどの家畜と牧羊犬が侵入するといった課題があります。そのような中で、家畜の数や、牧羊犬の数の調査は、生息地の周辺環境を把握するうえで重要な情報になります。
「特にマナヅルのヒナが小さいうちは、マナヅルの巣がある湿地帯に犬や家畜が巣に近寄らないように、家族と一緒に工夫しているんだ」
遊牧民のご家庭の子どもたちも多く、ツルだけでなく人や家畜にとっても湿地環境が大切なことをよく知っています。
年間を通じて降雨量の少ないモンゴルでは特に、湿地が貴重な水源にもなっているのです。
マナヅルなど野生生物が生息できる健全な湿地環境を守ることは、人々の持続可能な暮らしにもつながります。
このほかにも、エコクラブの子どもたちは、マナヅルのモニタリングや観察会など、さまざまな活動にWWFと共に取り組んでいます。
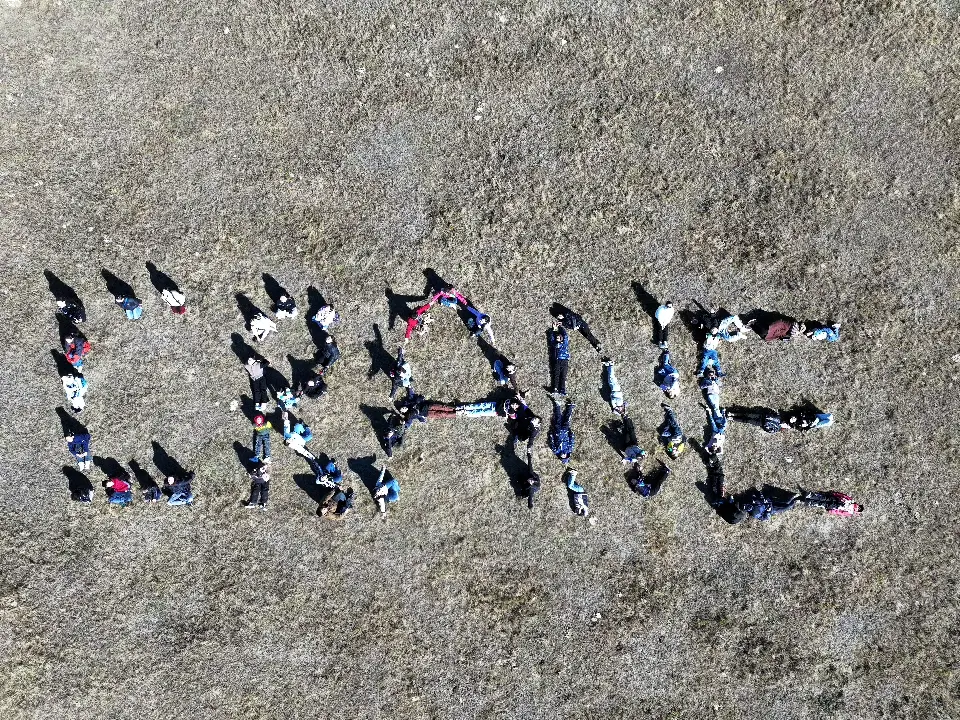
観察会に参加した皆で、大きく「CRANE(ツル)」の文字を表現。

観察会の様子。マナヅルたちを刺激しないよう、双眼鏡や望遠鏡を用い、遠くから観察します。
活動の結果、2024年には、これまで繁殖に成功していなかった場所で、2羽の幼鳥が無事に育っているのを確認することができました!

マナヅルのヒナのきょうだい。 特にモンゴルや中国で繁殖する個体数は減少傾向にあるとされており、1羽1羽が無事に生まれ育っていくことが重要です。
これからも、私たちは、子どもたちをはじめ地域コミュニティの皆さんと協力し、人と自然の共生を目指して、マナヅルと湿地の保全活動に取り組んでいきます。

春、モンゴルで生まれ成長したマナヅルたちは、寒い季節になると、中国、韓国、そして日本の越冬地に渡ってゆきます。繁殖地だけでなく越冬地や中継地の環境も同時に保全していくことが重要です。フライウェイ(渡りのルート)にある国々での連携をさらに強化していきます。