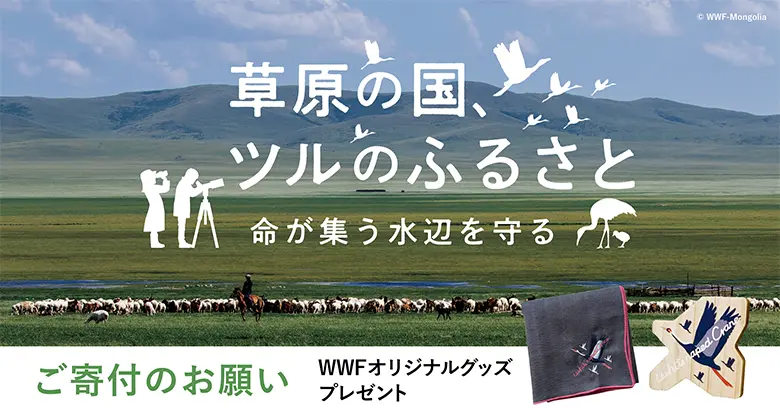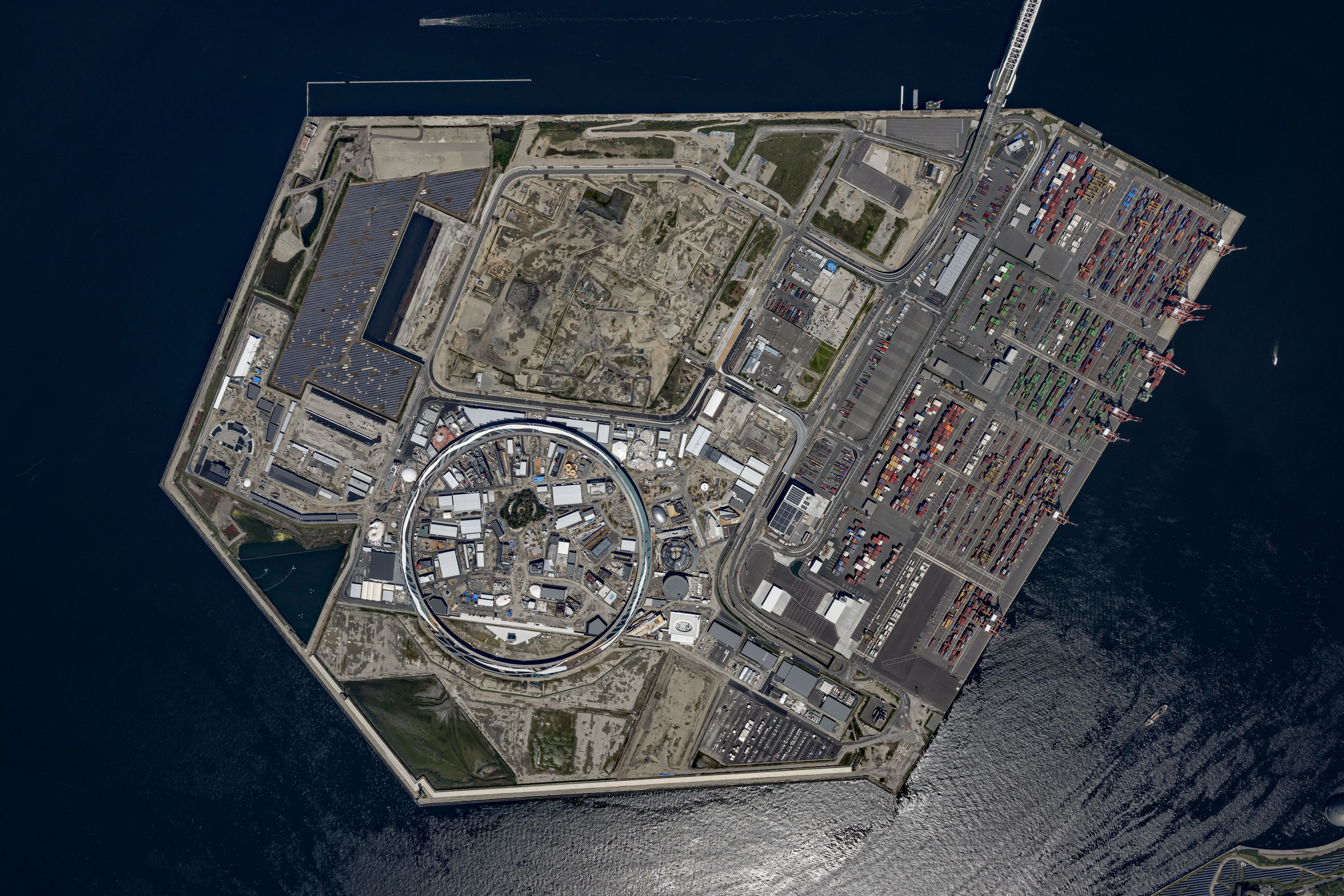「世界湖沼の日」ツルが集うモンゴルの渓谷
2025/08/27
今日8月27日は、「世界湖沼の日(World Lake Day)」。
昨年12月の国連総会で制定され、今年初めてその日を迎えます。
「世界湖沼の日」は、各国や国際機関が湖沼の重要性を認識し、力を合わせて湖沼および関連する生態系を持続可能な形で維持・保全・再生していくことを目指したものです。
そんな記念日の今日は、モンゴルの湖沼について紹介したいと思います。

ここはモンゴル東部にある、ハルハ・フイテン渓谷湖沼群。4万ヘクタール以上*の広大な谷あいに、小さな湖沼が点在する、ラムサール条約の登録湿地です。
*4万ヘクタール以上:ラムサール条約湿地として登録されている面積。渓谷地帯全体だと約2億ヘクタール。
ハルハ・フイテン渓谷湖沼群は、鳥類の楽園。
167種の鳥類が確認されており、湖沼とその周辺の湿地帯は、特にツル類にとって世界的に重要な生息地となっています。
これまでに、マナヅル、クロヅル、ソデグロヅル、アネハヅル、ナベヅル、タンチョウの6種ものツルが観察されました。(タンチョウは一度のみ確認)
なかでも、マナヅルとクロヅルは、この地で毎年繁殖しています。

マナヅル:IUCN(国際自然保護連合)レッドリストでは「VU(危急種)」とされています。推定個体数は6,700~7,700羽。日本の九州にも冬鳥として毎年飛来します。

クロヅル:IUCNレッドリストでは「LC(低危険種)」。アジアからヨーロッパにかけて広く生息する、ツル類では最もポピュラーな種です。日本にも冬に、少数が渡ってきます。

ソデグロヅル:IUCNレッドリストでは「CR(近絶滅種)」に選定され、ツル類では最も絶滅の危機が高い種です。ここでは繁殖はしていませんが、渡りの旅の中継地として、渓谷の湖沼群は重要な場所になっています。

アネハヅル:IUCNレッドリストでは「LC(低危険種)」。少し小型のツルで、頭に独特な飾り羽があります。日本にも少数が飛来することがあります。

ナベヅル:IUCNレッドリストでは「VU(危急種)」。マナヅルと共に、冬を日本で過ごす渡り鳥です。

タンチョウ:IUCNレッドリストでは「VU(危急種)」。この渓谷周辺での記録は稀ですが、中央アジアの湿地帯は、タンチョウにとって重要な繁殖地です。日本の北海道にも生息しますが、こちらの個体群は「渡り」をしないため、大陸の個体群との交流はありません。
ツル類をはじめ、多種多様な水鳥が暮らす、ハルハ・フイテン渓谷湖沼群。
しかし、この地は今、気候変動と家畜の過放牧による脅威にさらされています。
もともと降雨量の少ないモンゴルは、年間の降雨量が日本の5分の1以下。気候変動の影響を受け、年によってはさらに降雨量が減り、湿地が消失することもあります。
また、水源である河川や湖沼の周辺では特に、家畜が集中的に放牧されています。放牧自体は、モンゴルの遊牧民の人々にとって、伝統的な文化と暮らしの一部ですが、近年、毛織物や乳製品などの需要の増加によって過放牧が起き、湿地の水量・水質に影響を及ぼしています。

小さな水源に集まる家畜たち。ウシ、ウマ、ヒツジ、ヤギなどが放牧される。
私たちが2024年よりWWFモンゴルと連携して実施している、マナヅル保全プロジェクトでは、放牧をして暮らす遊牧民の方々と協力しながら、これらの課題に取り組んでいます。
重要湿地の調査、子どもたちと連携した地域への働きかけ、水源保全活動などの取り組みを通じ、少しずつ状況が改善している現場も。

湖の周辺にフェンスを設置することで、家畜の侵入を防ぐ取り組み。この取り組みにより、水量が増え、フェンス以内の植生が回復し、マナヅルなど水鳥が繁殖を始めました。
マナヅルをはじめとするツル類やその他野生生物が生息できる健全な湿地環境を守る、そして、遊牧民の人々の産業・生活を持続可能なものとしていく。
皆さまのご支援に支えていただきながら、そんな思いを胸に、人と自然が調和して生きられる社会を目指して活動していきます。