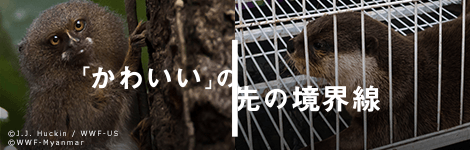ロシア・ソチでのワシントン条約第70回常設委員会会合が閉幕
2018/10/12
ワシントン条約常設委員会の開催
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」、通称「ワシントン条約(CITES)」。その名の通り、絶滅の危機にある野生生物の輸入や輸出を規制することで、生息国で生じる密猟や過剰な利用を抑え、保護することを目的とした国際条約です。

そのため、ワシントン条約の会議では、どの野生生物を、どれくらいの厳しいレベルで取引規制の対象とするのか、激しい議論が戦わされます。
このワシントン条約の締約国会議(COP)は、2~3年ごとに開催されますが、これとは別に毎年、「常設委員会」が開催されています。
関係する科学委員会や各国からの報告、また緊急に検討しなければならない案件など、COPだけでは処理できない議論や検討が必要な内容が多くあるためです。

CITES-SC70会場の様子。各国政府団とNGOが同室に席を並べて議論を行ないます。

議長席。議長は、各国から出されるさまざまなコメントをその場でさばき、議論をリードしていきます
NGOの参加とその意味
今回ロシアのソチで開催されたこの常設委員会の会合は、第70回目の開催となり、およそ80カ国から総勢700名以上の国の代表と、WWFやTRAFFICといったNGO(民間団体)が100団体以上参加しました。
この会議はCOPと同じく、議題を提案できるのはあくまで締約国と科学委員会、事務局に限られます。さらに会議で決定権を持つのはCOPで地域代表に選出される一部の国のみ。NGOはあくまでオブザーバーとしての参加になります。
それでも、NGOには発言することが認められており、各国に対して、会議に挙げられている提案や報告事項の中で不足している情報や、活動から見出した新たな懸念などを述べることができます。

オブザーバーが発言をする時は、座席票であるプレートを掲げます
議論が公平に進み、また、野生生物の保全活動が世界の協力の下で促進されるように、国境を越えた立場から、各国の代表団と同じ会場に席を並べ、議論を追いながら、発言することは、NGOに期待される大きな役割です。
そしてこの内容は、いずれも次回のCOPに引き継がれることになるため、国際会議の位置づけとしても、とても重要な会議です。
第70回常設委員会会合の結果を受けて
今回のソチでの会合でも、条約の財政や、各国が戦略的に取り組むべき施策の検討、そして、取引規制の対象となるそれぞれの「種(しゅ)」に関係した、多岐に渡る議題が議論されました。
それぞれのタイトルにはゾウ、トラ、サメ、ローズウッドなど、実際の種名も多く並びますが、いずれも違法取引、密猟、特に問題のある国についてなど、深刻な内容ばかり。

アフリカゾウ(Loxodonta africana)

カメルーンで押収された象牙

2012年にアフリカ中部、カメルーンのブバ・ンジダ国立公園で密猟されたアフリカゾウ。紛争に付け込んで行なわれたこの時の密猟では、一度に200頭ものアフリカゾウが犠牲になった。象牙を売って得た利益が、武装グループなどの軍資金に充てられているという報告もある。
議題の増加はそのまま、野生動植物の置かれている状況が厳しく、解決しなければならない課題が多いことの証とも言えます。
1975年のワシントン条約の発効を受けてWWFとIUCN(国際自然保護連合)が設立した野生生物の違法取引を監視するTRAFFICは、これまでにも国際取引に関する調査・モニタリングの結果について報告を行ない、条約の施行においても重要な役割を果たしてきました。
今回の会議へ向けても、日本と中国でそれぞれ新たに象牙取引に関する調査を実施。現地ではその結果をまとめた報告書を、最新の状況をお伝えするものとして発信しました。
本会議では、開催前から話題になっていた日本の調査捕鯨をめぐる議論や、象牙の国際取引の規制についても、検討が行なわれ、それぞれ注目すべき動きがありました。
議論された内容の抄録は、現地で会議に参加したスタッフより、後日あらためてご報告いたします。
この常設委員会での結果を受けて、2019年5月にはスリランカのコロンボで、ワシントン条約の第18回締約国会議(COP18)が開催されます。
世界の野生生物の保護に向けた、建設的な議論が展開されるように、WWFとTRAFFICは引き続き、調査活動と各国政府への政策促進の働きかけを続けていきます。

今回の会場のあるソチは2014年のオリンピック・パラリンピック開催地。カフカス山脈に囲まれた自然豊かな場所です。