企業による野生生物のオンライン取引対策:象牙
2025/11/19
- この記事のポイント
- 違法性の疑われる象牙製品が取り扱われるなど、課題が指摘されてきたオンラインでの象牙取引において、主要なCtoCプラットフォームを運営する複数の企業が、象牙にかかわる出品ルールを改定。自主的な取り締まりの強化に踏み切りました。2025年11月24日から開催されるワシントン条約第20回締約国会議に向けて、日本の象牙市場が注目される中、この業界による取り組みは歓迎すべき内容です。どのような改訂が行なわれたのか、詳細を解説します。
象牙にかかわる新たなオンライン取引対策
オンラインでのCtoC取引プラットフォームを運営する株式会社メルカリ(以下、メルカリ)の「メルカリ」、そして、LINEヤフー株式会社(以下、LINEヤフー)が運営する、「Yahoo!オークション」および、「Yahoo!フリマ」において、象牙にかかわる出品ルール(運用やガイドライン)が改定されました。
メルカリは2025年10月30日から、Yahoo!オークションとYahoo!フリマでは2025年11月10日から、それぞれ運用が開始されています。
メルカリもLINEヤフーも、それぞれ2017年と2019年に自社の運営するオンライン・プラットフォーム上での象牙取引を禁止する自主ルールを既に定めています。
今回は両社共に、追加措置として、「象牙類似品」について新たな運用を開始するというものです。
これは、象牙取引禁止の自主ルールを定めて以降続いていた課題に対処するもので、抜け穴となっている行為を防止する予防的措置として、歓迎すべきアクションです。
改定された出品ルールとは
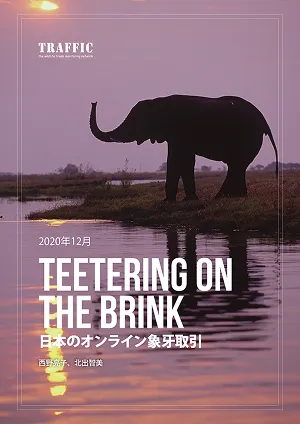
TRAFFICが2020年に発表したオンラインの象牙取引調査報告書『Teetering on the Brink』でも、「象牙風」としている商品の中で本物の象牙の可能性のある出品があることを指摘している
「象牙類似品」とは、象牙に似た素材(例えばマンモスの牙やラクト材など)で作られた製品のことですが、そうしたものは「象牙風」「象牙調」などとして出品されることが主流化しています。
しかし、そうした中に、類似品としながらも、実際には本物の象牙製品である、という出品が横行していることが問題になっていました。
2025年6月、象牙をマンモスの牙と偽って販売した象牙取り扱い事業者が逮捕(不正競争防止法違反)される事件も発覚しました。
不正競争防止法違反及び種の保存法違反事件被疑者等の検挙について(外部サイト)
こうした事態を重く受け止め、今回、自主的なルールを新たに定めた形です。
- 象牙に類似する商品出品時の注意喚起:象牙商品の取引が厳しく制限されていること/材質を明記することの警告表示の掲出
- 象牙でないことが明確に確認できない場合(出品者自身が材質を断定できない場合や真偽不明とする場合を含む)には削除対象とする
- 象牙に類似する素材を使用した商品には、材質が判断できる写真を掲載すること
- 商品の素材を明らかにすること
- 商品名に「象牙」を示唆する表現を使わないこと
- 商品説明に、「象牙」を想起させる表現を使わないこと
ガイドライン細則「33. 象牙類似品の出品に関するルール」(外部サイト):https://guide-ec.yahoo.co.jp/notice/rules/auc/detailed_regulations.html#C_33
※ルール策定の背景として、「環境保護の観点や社会的責任を踏まえ」ということが説明されている:ガイドライン改定のお知らせ(外部サイト)
日本の象牙取引
象牙の国際取引は1989年以降、原則禁止されています。しかし日本では、国内で合法的に売買をすることが可能です。
日本にはこの1989年以前に合法的に輸入した在庫が、今も多く存在し、象牙を取り扱う事業者が、事業者登録をして、在庫管理をしっかりしていくことを前提に、製造・販売をすることが認められています。
しかし、近年、日本にある在庫象牙が違法に海外に流出するなど、違法行為が散見され、国際的にも問題視されてきました。
日本にある多くの在庫と、それを利用した国内の合法的な象牙市場が、密輸の温床になる懸念と、需要を喚起し、新たな密猟の引き金になると、厳しい目が向けられてきました。
また、特に、匿名性が高く、誰でもが気軽に出品・出店できるオンライン取引を通じた違法事例も発覚。
違法取引の供給源となっていると指摘されたことから、取引の場を提供するオンライン・プラットフォームを運営する企業側での対策が進みました。
現在では、CtoC取引、BtoC取引双方において、日本の主要なオンライン・プラットフォームでは、国内の法規制を超えた、自主的措置として、取引禁止のルールを定め、オンラインでの象牙取引はできなくなっています。
これからの社会に向けて必要なこと
オンライン取引では、購入者が実際に商品を手に取ってみることができません。そのため、出品者が提供する情報と、画像を見て判断をするため、それらの情報が正しいことが前提となります。
この前提の下、各プラットフォームでは、象牙に限らず、法令遵守や自主ルールが守られているかのモニタリングを実施しています。
2025年6月に起きたマンモスの牙を象牙と偽った事件は、消費者保護の観点でも、また、安心・安全の場を提供するために実施している企業側の取り組みの観点でも、それぞれを反故にするものです。
国際的に国内象牙市場の在り方が厳しく問われている中で、事業者が行なった行為としても由々しき実態です。
象牙については、国内の法令で取引が禁止ではない中で、企業側の自主的措置の担保をする限界を浮き彫りにしました。
今回のそれぞれの企業での対応は、これまで判断が難しかった出品に対して、効果的なルール運用を目指す予防的措置として期待されます。
また、出品者に対しても、裏をかくような取引を許容しない、といった明確なメッセージとして、企業の取り組み姿勢を示すものとなりました。
2025年11月24日から、ワシントン条約の第20回締約国会議(CITES-CoP20)が開催されます。
ワシントン条約第20回締約国会議:ポータルサイト(外部サイト)
毎会議ごとに、アフリカゾウ保全に関する議題は多数挙がりますが、国内象牙市場に対する議題もそのひとつになっています。
CITES-CoP20では、日本に向けて、「狭い例外を設けて、国内取引を禁止する法的措置をとること」という内容の勧告提案も挙がっています。

ワシントン条約上の報告では、2019年以降ゾウの密猟・象牙の密輸は減少傾向にあるものの、大規模な密輸が未だに起きていることや、COVID-19パンデミック回復後の動向には注視が必要との見解が示されている
これまで日本政府は、日本の国内象牙市場は厳格に管理をされているため、合法的な市場を現状の形で維持する姿勢を示しています。
しかし、企業側が、講じるべき措置として取り組みを進める中、今一度、事業者の実態や、国内で縮小する需要など、日本の国内象牙市場について適正な評価をする必要があり、今後の象牙市場の在り方を見直す時がきています。
WWFジャパンでは、オンライン・プラットフォームの運営企業が進める、こうしたオンラインでの野生生物取引の課題への取り組みを後押しし、また、より持続可能な取引の促進に向けた働きかけを続けていきます。





















