西ヒマラヤにおけるユキヒョウ保護 活動報告(~2025年7月)
2025/10/31
- この記事のポイント
- WWFジャパンではユキヒョウ・スポンサーズの皆さまからのご支援のもと、WWFインドが取り組む西ヒマラヤに生息するユキヒョウの保全活動を推進しています。アジアとヒマラヤの高山に生息するユキヒョウを脅かしているのは、増加する家畜への被害によって生じる人との「あつれき」、そして獲物となる草食動物の減少や、気候変動による生息環境の変化です。現地から届いた、2024年7月から2025年6月までに行なわれた活動について報告します。
西ヒマラヤで進むユキヒョウの保護活動
標高4,000mを越えるヒマラヤ、カラコルムの山々に生息するユキヒョウは、世界的にもめずらしい高地の生物多様性を代表する野生動物です。
しかし、近年は高山帯でも開発や道路などの交通網の整備・拡大が進み、放牧される家畜も増えていることから、貴重な自然が失われつつあります。
また、気候変動(地球温暖化)による環境の変化は、ユキヒョウをはじめとする、高山の自然に適応した野生動物たちを、絶滅の危機に追い込んでいます。
この現状を改善するため、WWFインドでは、地域住民とユキヒョウなどの間で生じる「あつれき」を解消し、人と野生動物の共存を実現する取り組みを展開。
WWFジャパンも、日本の「ユキヒョウ・スポンサーズ」の皆さまのご支援のもと、WWFインドとその活動を推進しています。
その主な取り組みは、以下の5つです。
- ラダックに生息するユキヒョウの調査
- ラダック・チャンタンでの環境保全と野生動物保護およびパトロール活動の強化
- 人と野生動物の「あつれき」が生じている地域でのコミュニティとの連携の向上
- ユキヒョウとオオカミ、およびその獲物となる草食動物の保全活動にかかわる関係者の意識向上
- 西ヒマラヤにおける気候変動の影響に対する理解の促進
2025年8月に届いたWWFインドからの報告をお届けします。

野生動物の調査とその技術向上
前年、この取り組みでは、ユキヒョウとその獲物となる野生の草食動物の生息状況についての調査活動が、大きな進展を見ました。
これらの調査は、実際の保護活動の基礎になる、重要なデータを明らかにするものです。
2025年6月までの1年間については、こうした調査の技術レベルを向上させる取り組みに力を入れました。
特に2024年10月と12月の2回にわたり、西ヒマラヤ・ラダック地方のカルギルで、ワークショップを実施。
活動現場の最前線で活動するインドの野生生物保護局や森林局の職員を対象に、野生動物調査用のカメラトラップ(自動カメラ)の扱いデータの管理、分析など、調査活動を活かすための技術を習得する機会を提供しました。
また、カルギル周辺の地域で発生している、ヒグマがユキヒョウと同様に、家畜を襲う問題についても、取り組みを行ないました。
高山に生息するヒグマは数が少なく、保護が必要とされていますが、家畜を殺された報復に殺されるなど、地域住民との間で「あつれき」が生じるケースが少なくありません。
そこで、ユキヒョウの保護活動の手法に倣い、地域の関係者を集めたカルギルでは初の開催となる、ヒグマ保全に関するマルチ・ステークホルダー・ワークショップを、2024年12月26日に実施。
WWFインドの活動と今後の計画が共有され、カルギルにおけるヒマラヤのヒグマの共同保全計画策定に向けた検討が開始されました。

上段:ヒグマが家畜の囲いに空けた穴と、被害防除のための対策。下段:ヒグマの糞と自動カメラが夜間に捉えたヒマラヤのヒグマ。
地域参加によるパトロールと保全活動の広がり
ユキヒョウなど野生生物の保護活動への若者の関与を高め、その調査やパトロール活動を強化するため、WWFインドではラダックのチャンタン地方で「マウンテン・ガーディアン」を設立。
2025年6月までの取り組みでは、地元の若者8名がこれに参加し、訓練を受けて、現在進行中および将来の保全活動において重要な役割を担っています。
このうち6名はチャンタン周辺で、土壌や植生のサンプル採取、住民と野生動物の「あつれき」を緩和するための調査・検討に参加。さらに、地域で生じている気候変動による影響の評価にも取り組んでいます。
また、2名はカルギルでヒグマと住民の間で起きている「あつれき」の解消に向けた活動に積極的に参加。
さらに、2025年5月22日の「国際生物多様性の日」には、ラダック大学のカルギルキャンパスと保全ワークショップを開催し、WWFインドのスタッフが講演。西ヒマラヤの生物多様性と保全、そして人と野生生物の共存の促進に重点を置いたWWFインドの取り組みを紹介しました。
このワークショップでは、カルギルで新たに、ユキヒョウ保護のための「マウンテン・ガーディアン」に関係するネットワーク組織「ベア•ブラザーズ」の発足も決定。
これに参加する若者たちは、村や町で生じた「あつれき」などの情報収集や、被害防除のための機材のメンテナンス、パトロール活動についての訓練を受けることになりました。
こうした若者たちの関与により、地域に根ざした保全活動の取り組みが理解を得て、促進されています。

WWFインドはチャンタン地方でユキヒョウやオオカミと人の間で生じる「あつれき」を防ぐため、家畜の損失状況などを分析し住民と協議。被害の大きなエリアを中心に、肉食動物が夜、家畜に近づくのを防ぐため、400個以上の懐中電灯や20個の自動照明装置を配布しました。効果についての検証も予定しています。
「あつれき」の解消に向けた地域コミュニティとの取り組み
西ヒマラヤのラダック地方は、そのほとんどが森林限界を超えた高山帯であるにもかかわらず、品質の高さで知られるパシュミナなどの毛織物を生産するためのヤギやヒツジなどの家畜の放牧が盛んに行なわれてきました。
しかし近年、世界的なパシュミナの需要に応えるため、その原材料の毛を採るヤギ等の家畜の飼育数が増加。その放牧地も広がったことで、ユキヒョウが獲物とする野生の草食動物が家畜に生息域を奪われる問題が生じるようになりました。
その結果、草食動物自体の数も減少。これにより、ユキヒョウやオオカミが家畜を襲うようになり、逆に住民に害獣として駆除されたり、すみかを追われる「あつれき」の問題が深刻化しています。
WWFはこの問題の解決を目指し、ラダックのチャンタン地方で、牧畜を営む複数のコミュニティを対象に、「あつれき」の現状を含む社会的な現地調査を実施。その報告書を作成しました。
その結果、伝統に裏打ちされた暮らしを送るコミュニティの関係者は、高い幸福感を感じている(満足度71%)半面、物質的な幸福度(55%)や、経済的な幸福度(54%)については、満足度が依然として低いことが分かりました。
特に顕著だったのは、市街地とコミュニティのエリアを結ぶ交通網をはじめとしたインフラの脆弱性に対する不満です(満足度39%)。
家畜に被害をもたらす、ユキヒョウ、オオカミ、ヒグマといった野生動物への対策についての満足度も39%と低く、継続した取り組みの必要性が認められました。
一方で、そうした被害が頻繁に生じる地域であっても、これらの野生動物と共存することについては、回答者の50%が寛容な答えを示し、報復などのリスクが多少なりとも抑えられていることが分かりました。
これは、対象地域のチャンタンの住人がチベット仏教の信者で、伝統的に人と自然の共存を実践してきたこととも、関係があると考えられます。
こうした住民の意識を基盤として、今後はより迅速かつ科学的な「あつれき」の緩和策や補償を実現していく必要があります。
また、WWFインドでは、人と野生動物の共存に向けた、地域コミュニティが主体となったビジョンづくりにも取り組んでいます。
地方行政や地方議員、地域の住民や市民団体との協議を経て策定されたこのビジョン案は、アンケートの結果、その内容がチャンタン地域のニーズを反映しているとする回答が82%にのぼるほど、高い期待を集めるものとなりました。
そして2025年6月に開催した、このビジョン案を承認するステークホルダー会議には、地域の関係者をはじめ100名あまりが参加。
牧草地の保全と野生動物との共存に焦点を当てた、地域共通のビジョンに対し、全会一致の支持が表明されました。また、この会合では、そのビジョンを実現するための牧草地協議会を設立することも合意されました。
これらは、チャンタン地域で今後、長期的なユキヒョウの保全を実現していく上での重要な布石となるものです。

ラダックの女性たちが手掛ける毛織物。地域の暮らしを支え、経済的なゆとりを醸成することで、野生動物との「あつれき」を緩和する手立てとして、これらの生産を手掛ける女性への支援も行ないました。チャンタン地方の9つの村で、支援の一環として行なった、高値で売れる毛織物の生産研修を受けた女性の数は、今期196人に上りました。
ユキヒョウ保全に対する意識の向上を目指す取り組み
前年に実施した、肉食動物とその獲物となる草食動物(野生のヤギ、ヒツジ類)の生息状況についての2つの調査結果をまとめました。
1つ目の肉食動物の生息調査結果からは、ラダック地方のハンレでは、ユキヒョウの生息密度が100km2あたり0.52頭と推定されました。
この数値は、インドのヒマラヤに生息するユキヒョウ個体群の中では、最も高い水準です。
一方、ユキヒョウの主な獲物であるバーラル(ブルーシープ:Pseudois nayaur)の生息密度は、100km2あたり4.64頭、チベットガゼル(Procapra picticaudata)は2.70頭と、いずれも低い数値を示しており、これを探して狩りをするユキヒョウの行動圏を拡大させる一因になっていると考えられます。
これらの草食動物は、草地の環境の健全性を示す指標となる動物でもあるため、その生息状況についての情報は、今後の保全計画の中でも重要な要素として取り入れる必要があります。
このラダック地方における今回の調査研究は、他の国々を含む生息域全体におけるユキヒョウの行動や生態についての研究結果と比較することで、新たな知見を確立し、この種全体の効果的な保全戦略を策定することにも貢献するものです。

2024年10月23日の「世界ユキヒョウの日」には、ユキヒョウと自然保護の重要性について若者に伝える大きな催しを複数実施しました。ギャの町の公立高校では、ユキヒョウの生態学的な重要性をテーマにしたインタラクティブなセッションを開催。その後、実際の生息地をトレッキングし、ラダックの自然の美と生態系、保全の役割を学びました。
西ヒマラヤにおける気候変動の影響調査
ヒマラヤは世界で最も気候変動の影響を強く受ける自然環境の一つであり、その深刻化はユキヒョウの未来を左右する重要な課題です。
WWFインドでは、特にラダックのチャンタン地方における気候変動の影響について、直接収集した一次データと二次データに基づき、地域が抱える脆弱性について評価を行ないました。
| 調査内容 | コミュニティの気候変動に対する脆弱性 |
|---|---|
| 調査対象 | 27集落の156世帯 ・牧畜世帯:62世帯 ・兼業牧畜世帯:94世帯 |
| 調査地域 | 西ヒマラヤ・ラダックのチャンタン地域 中央部(56地点)、北部(36地点)、南東部(44地点)、南西部(20地点) |
| 方法論 | 気候脆弱性指数(CVI:影響の有無、内容、適応力の3要素)を用いて生計手段と地域の2面から分析。 |
その結果、牧畜のみを営むコミュニティは、観光などを兼業している牧畜コミュニティよりも、気候変動に対し37%も脆弱であることがわかりました。
これは、牧草地の環境が氷雪の解けた水に依存しているため、気温の上昇による影響をより強く受けているためと考えられます。
兼業で牧畜を営むコミュニティの場合は、ホームステイのような観光客の受け入れなどを通じ、代替的な生計手段も持っているため、より高い適応能力を有しています。
地域別でみると、南東部が気候、水不足、放牧地の制限などによって、他地域と比較して30%脆弱性が高い傾向があります。
一方、インフラが整備され、収入源が多様化している中部では、脆弱性が他地域より20%低いことが明らかになりました。
しかしいずれも、水不足や牧草地の劣化、家畜の生産性の低下などが主要なストレス要因として認められており、こうした問題はユキヒョウと人間の間で生じる「あつれき」を、さらに深刻化させる可能性があります。

担当スタッフより:ユキヒョウの未来のために
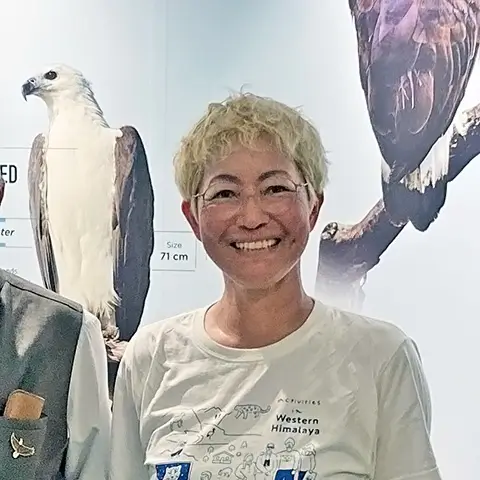
西ヒマラヤ・ユキヒョウ保護プロジェクト担当 若尾慶子
私たちの西ヒマラヤ・ラダックでのユキヒョウ保護活動を、応援くださっている皆さま、いつも温かいご支援をいただき、ありがとうございます。
ヒマラヤの山々の現場で日々、活動に取り組んでいるインドの仲間たちと共に、この場をお借りして、心より感謝を申し上げます。
早いもので、このユキヒョウの保護プロジェクトが始まってから4年が経ちました。現場では、最初の一年目に築いた人と支援のつながりが、翌年の活動や調査につながり、今ではさらに、それを基にした取り組みとビジョンを生み出しています。
ユキヒョウに限らず、野生動物の保全には長い時間が必要とされますが、このプロジェクトがその歩みを着実に進めている姿を見られることは、本当に幸せなことだと感じています。これは、WWFの会員の皆さま、そしてユキヒョウ・スポンサーズの皆さまの継続的なご支援の賜物です。
現場では今も、さまざまな課題の解決に向けた挑戦が続けられています。また、気候変動のような規模の大きな問題も、今後深刻化することが懸念されます。その中で、人と野生動物の共存を実現することは、容易ではありません。
野生のユキヒョウの未来を守るために欠かせない、さまざまな活動の実現に向けて、これからも私たちWWFジャパンは、WWFインドの仲間たちと協力しながら、力を尽くしていきたいと思います。
ぜひこれからも、WWFの取り組みにご注目とご支援をいただければ幸いです。

「野生動物アドプト制度」リニューアルのお知らせ

WWFジャパンは、さらにご支援の輪を広げていくため、「野生動物アドプト制度」を2025年11月19日よりリニューアルいたします。
現在ご支援いただいている皆様は、新たなお手続きなく、これまで通りのご支援額・ご支援方法でご支援を継続いただけます。
また、リニューアル後より公式サイトの「マイページ」にログインいただくことで「スポンサーズオンライン特典」をご利用いただけます。
次回更新時にリニューアル版に契約変更することで「スポンサーズ初回特典」もお受け取り可能となります。更新時期が近づいたら、再度ご案内します。
詳しくは以下リンクからホームページをご確認ください。
野生動物アドプト制度リニューアルについて詳しくはこちら






















