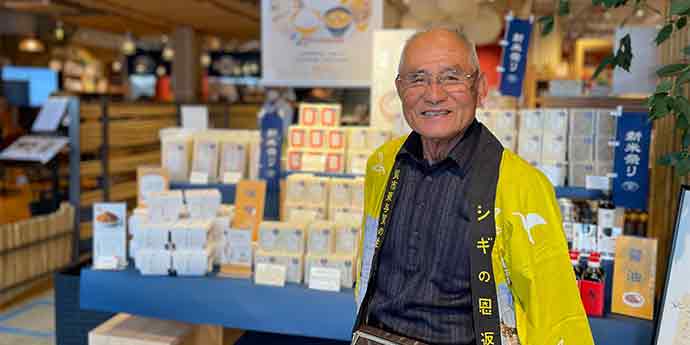日本のコメ政策の転換点 増産推進の中でも水田生態系保全との両立を
2025/08/07
8月5日、石破首相はコメの増産に向けた政策の転換を発表しました。
これは、長年のコメの「減反」やその後の事実上の生産調整を、今後「増産」に転じる方針を明らかにしたものです。
「令和の米騒動」に端を発したこの政策の大転換は、コメの生産・流通量を増やすことはもちろん、コストの抑制や、時代に合った新たな農業の模索を目指すものといえるでしょう。

これは、日本人の暮らしにとって非常に重要な政策ですが、その推進のポイントとなる「農業経営の大規模化・法人化やスマート化の推進などを通じた生産性の向上」は、身近な田んぼの自然やその構成要素である水生生物にも、影響を及ぼす可能性があるものといえます。
田んぼの景観は昔から、人とさまざまな生きものたちが共存する、重要な場となってきました。
湿地を保全する国際条約「ラムサール条約」でも、田んぼは保全すべき二次的な自然(人工的な自然環境)として規定しています。

しかし、「とにかく田んぼが広がればいい」というものではありません。
田んぼの自然を守るためには、さまざまな生物が生育・生息する水路やため池、農薬の使用を抑えたコメ作りなどが必要だからです。

すでに、全国的にコンクリートを多用した水田や水路の整備が進んだことで、ミナミメダカのような身近だった生きものたちが、絶滅危惧種に指定されるようになりました。
希少な生物が今も生育・生息する水田の環境は、地域の貴重な資源であり、未来世代につなぐべき財産でもあります。
またその一方で、生産者の高齢化や気候変動を背景に、整備された水田・水路が求められるのも事実です。
政策の転換を受けて、より生産性やコストを優先した農地整備が進められる中で、地域の生物相にも目を向け、生物多様性保全との両立、「ネイチャーポジティブ」の推進に寄与するコメ作りの在り方が検討されることを期待します。