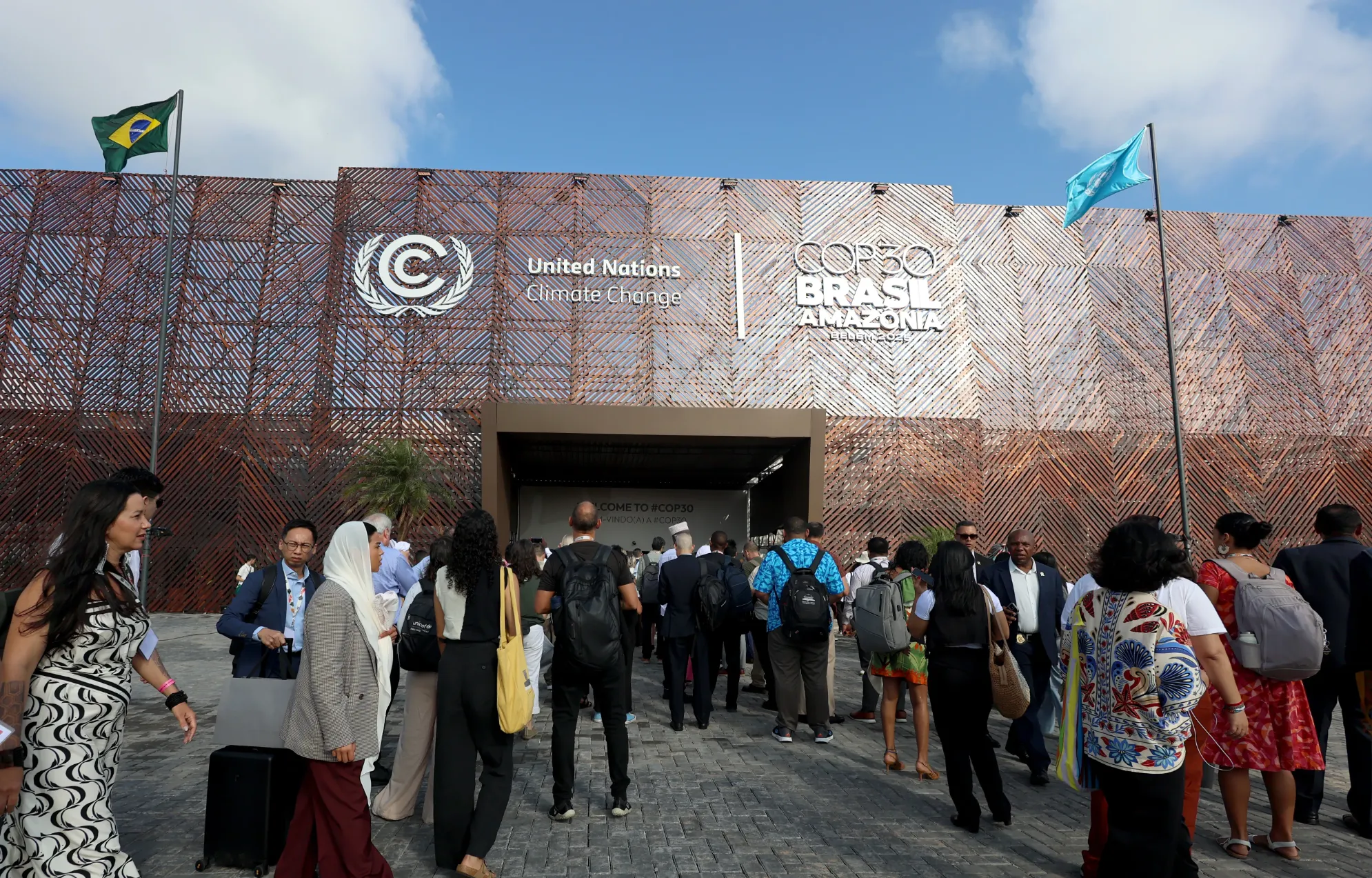再エネ拡大へ向けた、最前線の現場から
2017/03/06
こんにちは、広報の松岡です。
春が近づいてきたとはいえ、まだ寒さの厳しいこんな時期には、ぬくぬく暖かな暖房機器が欠かせませんね。
一日を通して考えてみても、暖房、照明の点灯、そして消灯と、私たちが何気なく使用する電気の量は、時間帯や天気、また季節により刻々と変動しています。
しかし発電所の電気は基本的に貯めておけないので、電力会社は必要な電力の量に応じて予測と調整を繰り返して発電し、安定した供給を行なわねばなりません。

特に、地球温暖化を防ぐ上で欠かせない、太陽光や風力、地熱や水力などの「再生エネルギー」活用拡大のためには、火力など他の発電手段の長所短所も考えながら、綿密な運用計画を策定することが、大きな鍵となります。
そこで先日、WWF温暖化担当の小西雅子が、2016年5月4日に供給電力中の再生可能エネルギー割合78%を達成した、九州電力株式会社へ取材に行ってきました!

これは、雑誌「隔月刊 地球温暖化」中の連載「小西雅子インタビューシリーズ paint a future~持続可能な未来をつくる主役たち」の第2弾。
記事中では、「再生可能エネルギー固定価格買い取り制度(FIT)」の開始後、一度は新規の太陽光発電申込を保留すると発表した九州電力が、その2年後には一時的に自然エネルギー78%を達成するまで、現場の最前線で試行錯誤してこられた方々の苦労や想いが紹介されています。
こうして自然エネルギーの活用拡大へ向け努力されている方々とその取り組みに光をあてることで、より多くの方が関心を持ち、日本の電力が変わっていく力になったら嬉しいなと思います。
今回の取材内容は、「隔月刊 地球温暖化」1月15日発売号と、3月15日発売号の2回にわたり掲載予定ですので、ぜひご覧ください!

取材後に、九州電力の皆さまと。左から2人目がWWFジャパン温暖化担当の小西雅子