企業による資源の持続可能な利用
自然界のさまざまなサービスや資源により成立する企業活動。その基盤となる環境と資源を、どのように持続可能な形で利用し、事業自体も継続してゆくかが、これからの「グリーンエコノミー」を実現させるためのカギになります。WWFはそうした企業の取り組みを支援するとともに、そのための国際的な認証制度等の整備・推進を行なっています。
環境と企業活動の母体を守ってゆくために
企業活動は自然界のさまざまなサービスにより成立しています。
原材料としての木材や水産物、水資源、さらにこうした物質的なサービスだけでなく、洪水や土砂崩れといった災害も、自然環境の破壊や劣化に起因していることが少なくありません。
また、自然資源は再生産されるものですが、その再生の母体にまで影響する形で、過剰な利用を続ければ、いつか枯渇してしまいます。
持続可能な形での入手を実現するためには、利用のありかたを慎重に考え、長期的な視野に立った管理を実践してゆかねばなりません。
野生生の物を含めた農林水産物等の資源についても、現在取り扱い、消費しているものが、どれくらい持続可能な形で利用できているかを、自社のみならず、海外の生産地まで含めたバリューチェーン全体で、積極的に確認し改善することが必要です。
WWFはそうした企業の取り組みを支援するとともに、第三者による認証制度を利用した、客観的な立場からの評価と改善を行なうための、国際的な仕組み作りを行なっています。
自然資源の価値を適正に評価・管理することを通じて、自然(生物多様性)を守ると同時に、貧困撲滅に貢献する成長や雇用機会を生み出す、それが、WWFの目指すグリーンエコノミーです。
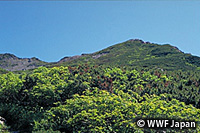

(C)WWF-Canon/WWF-Switzerland/A. della Bella
資料案内
関連情報
森林資源の持続可能な利用とFSCについて
森林資源の責任ある調達方針に基づき、環境や社会に配慮されていることが確かめられているFSC認証製品などを優先的に購入すること、森林破壊や劣化につながる製品を排除することで、森林保全と森林資源の活用の両立に貢献することができます。
水産資源の持続可能な利用とMSCについて
持続可能な調達を目指すうえで、企業も主体的に持続可能な水産物市場の構築を目指した取り組みが重要となってきています。 WWFではMSCの認証制度の普及などを通じた、適切な資源管理の促進に取り組んでいます。
パームオイルの問題とRSPOについて
製品に利用されているパーム油の中には、熱帯の貴重な自然や、森に依存して生活する人々の暮らしを犠牲にして生産されたものが、少なからず含まれています。この問題に取り組むため、「持続可能なパーム油」の生産と利用を促進する非営利組織、「持続可能なパーム油のための円卓会議」(RSPO)の設立を支援し、現在もその普及に取り組んでいます。
大豆栽培とRTRSについて
大豆栽培とRTRSについてこの数十年、大豆の栽培地は森林や草原、サバンナ等に進出し、これら重要な自然生態系を農地へと転換してきました。WWFは、生物の多様性と重要な生態系を守りながら、大豆等農産品の需要を満たすために、責任ある大豆生産に関する円卓会議(RTRS)を軸とした解決策を提唱しています。
野生生物取引の問題とCITES、フェアワイルドについて
ワシントン条約対象種でなくとも過剰な取引・利用をつづければ将来的にこの条約が保護しなければならないことになるかもしれません。このようなことにならないよう、企業は、野生動植物の持続可能な利用への配慮が求められます。

人と自然が調和して
生きられる未来を目指して
WWFは100カ国以上で活動している
環境保全団体です。

