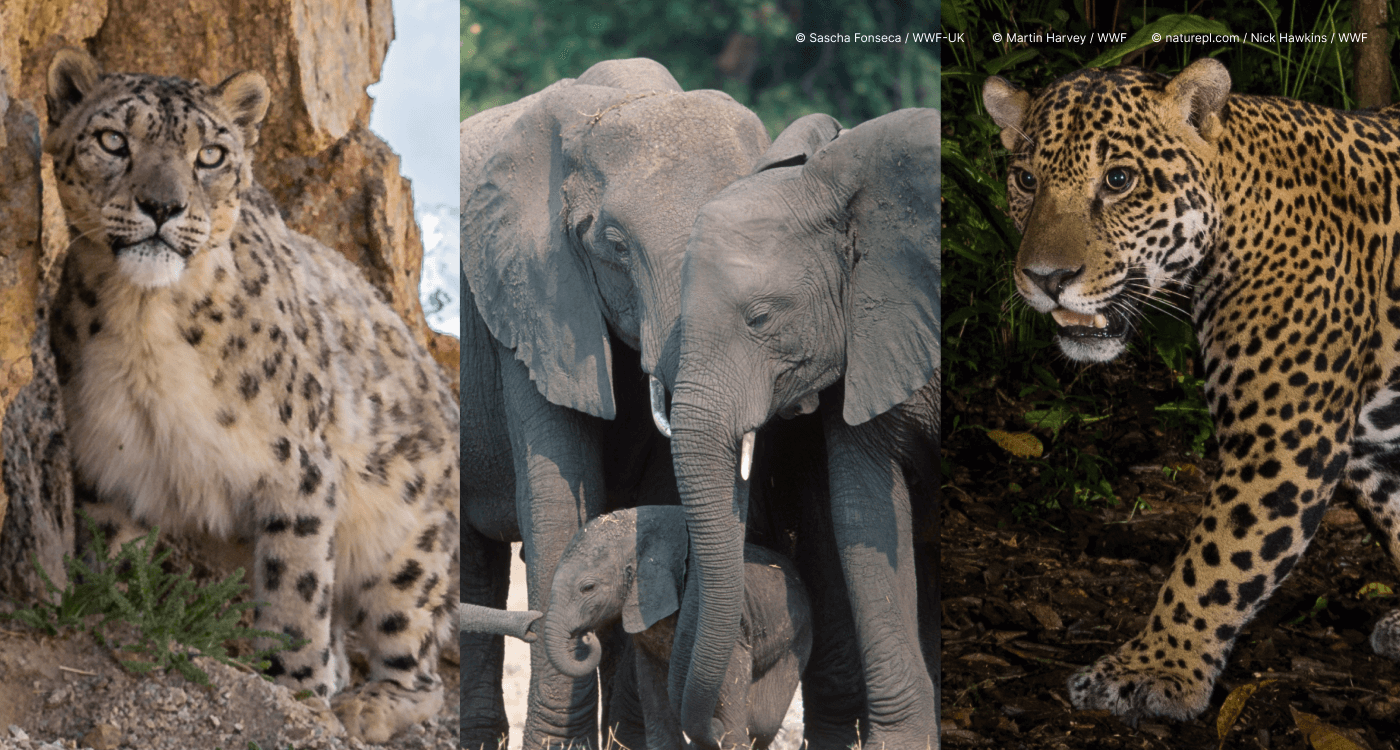「国内希少野生動植物種」の指定を提案
2019/03/20
市民も提案できる「国内希少野生生物」
日本の絶滅の恐れのある野生動植物を守る法律「種の保存法(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)」。
2017年2月、この法律が改正され、日本の野生生物を守る上で、大きな前進がありました。
WWFジャパンをはじめとする日本国内の自然保護団体の提案と働きかけにより実現した、主な改正のポイントは、次の通りです。
- 「絶滅の恐れのある野生動植物の種の指定提案制度」が法定化されたこと
- 「特定第二種国内希少野生動植物種」制度が創設されたこと
- 「希少野生動植物種専門家科学委員会(科学委員会)」が設置されたこと
まず第一点の「絶滅の恐れのある野生動植物の種の指定提案制度」が法定化されたことにより、種の保存法が指定する「国内希少野生動植物種(国内希少種)」に、どのような野生動植物を加え、また削除するのか、これを、市民や民間の団体でも、国に対して提案ができるようになりました。
レッドリストの基準で選ばれる「絶滅危惧種」などとは異なり、「国内希少種」は国が法的な保護対象とする野生生物です。
つまり、この指定が実現すれば、対象種の捕獲や販売、飼育などは、規制や禁止の対象となります。
そして、この制度を利用した第一回目となる、国内希少種候補の提案の受付「国内希少野生動植物種の選定又は解除に関して提案の募集」が、環境省により、2019年1月10日から2月28日の日程で行なわれました。
おびやかされる日本の野生生物
WWFジャパンは今回の募集受付にあたり、日本の固有種を含めた10種の野生生物について、この提案を行ないました。
このうちの5種は、近年、急激な消失と劣化の危機にさらされている、水田や水路などの二次的自然にすむ淡水魚です。

日本を代表する景色の一つ、里山の風景。
提案の根拠としたのは、WWFジャパンが現在取り組んでいる、「水田・水路の生物多様性と農業の共生プロジェクト」の中で、佐賀県・福岡県・熊本県に広がる、九州北西部の水田地帯の調査結果。
九州大学の鬼倉徳雄先生のご協力のもと、149地点で行なわれたこの調査では、特に水田や水路の環境を利用する、絶滅の恐れのある魚種が多数確認されました。
また、こうした魚類の生息に適した、昔ながらの土の水路などの環境が、各地で失われており、今後絶滅する種が増えてくる可能性があることも、あらためて明らかになっています。

九州北西部に広がる水田地帯での魚類調査。日本の固有種だったり、こうした環境でのみ生きる魚たちが今も息づいています。
残りの5種は、特に沖縄島や八重山諸島などを含めた南西諸島に生息する、日本固有のトカゲやカメといった爬虫類。
これらはいずれもペットとして人気があり、海外にも密輸されている例が報告されている野生動物で、インターネット上の通販などで売買されている例も確認されています。

沖縄島北部の亜熱帯林「やんばる」。国際的にも希少な野生生物が数多く生息していることが知られていますが、ペットなどを目的とした密猟や密輸(違法取引)が今も後をたちません。
「特定第二種国内希少野生動植物種」への指定を提案
WWFジャパンでは今回、この10種のうち1種を「国内希少野生動植物種」、9種を「特定第二種国内希少野生動植物種」として「種の保存法」の対象とするよう提案を行ないました。
この「特定第二種国内希少野生動植物種」も、2017年の法改正で導入された制度です。
それまで指定できる項目は、「国内希少野生動植物」の一つでしたが、この改正では、ほかにも規制の厳しさに応じ「第一種」と「第二種」の2つが新たに設定されることになりました。
この「第二種」は、水田を含めた里地・里山などの二次的自然に主に分布する絶滅危惧種を保全するため設定されたものです。身近な自然の中での保全を実現するため、規制内容がゆるく、観察会や調査などの機会に捕獲などが可能な形になっているのが特徴です。
WWFジャパンでは提案した10種の中に、二次的自然を利用して生きる野生動物が多く含まれることから、今回はこの「第二種」としての指定を提案しました。
もちろん、「第二種」であっても、指定されれば、ペット目的での捕獲や売買は禁止。また、危機のレベルがさらに上がった時は、「第一種」や「国内希少野生動植物」に格上げするよう、再度の提案を行なうことも可能です。
「科学委員会」の審議を経て
今回の提案は、2019年度の環境省の審議会として位置づけられている「希少野生動植物種専門家科学委員会(科学委員会)」で審議されて指定すべきかどうかが決まります。
この科学委員会も、「種の保存法」の法改正を求める活動の結果として、新たに設置されることが決まったもの。
この審議の結果が出るのは2019年4月以降となる見込みです。
そして実際に、指定された種が法的な保護下に置かれるのは、科学委員会の審議結果が公開され、パブリックコメントに掛けられてからとなる見込みです。前回の法改正の成果が注目されるところです。
どれくらい厳しく保全するのか、そのレベルも判断しながら、市民や民間の自然保護団体が、それぞれ危機にあると考える野生生物を、「国内希少野生動植物種」に指摘できることは、各地で生じている危機の現状をつぶさに集め、優先して保全すべき種を見定めていく上で、有効な手段といえます。
野生生物を保全する活動のフィールドは、必ずしも野外だけではありません。国全体の自然保護にかかわる法制度を改善し、その結果を通じて、実質的な変化や改善を求めていくことも、重要な「現場」の取り組みです。
WWFジャパンでは今後も、法制度の改善と希少種の保全について、政府や行政に対し、働きかけを行なっていきます。

*今回、WWFジャパンが提案した10種の希少な野生生物の種名は、生息地での密猟や取引を助長する可能性があるため、開示しておりません。ご了承ください。